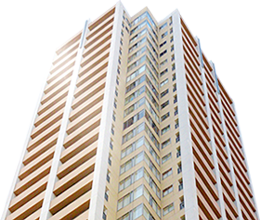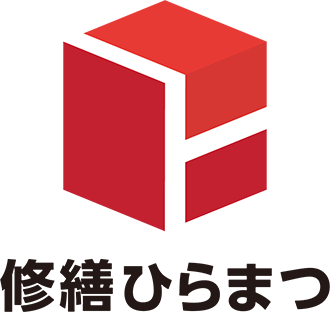修繕資金の負担を軽減!名古屋市で利用できる融資・利子補給制度の活用ガイド

名古屋市で分譲マンションの修繕を計画されている管理組合の中には、「積立金が足りず必要な修繕を先延ばしにしている」ケースがあります。現場で話を伺っていると、資材や人件費の高騰により「数年前に立てた長期修繕計画の金額では足りない」というケースも珍しくありません。
工事を延期すれば、その場の支出は抑えられるものの外壁や防水層などの劣化は進みます。結果、高額な工事になってしまうため早めの対応が必要です。とはいっても、工事費用が重くてすぐに着手できないケースもあると思います。
その場合は、名古屋市の「融資・利子補給制度」がおすすめです。「市が金利の一部を負担してくれる」ため、毎月の支払利息を減らせます。今回のお役立ちブログでは、名古屋市の融資・利子補給制度の内容をお話ししながら、ポイントなどを見てみましょう。
補助金や助成金と組み合わせて資金調達全体を最適化したい管理組合様も多いため、融資・利子補給制度と並行して検討しておくことをおすすめします。
▼合わせて読みたい▼
大規模修繕で使える補助金・助成金の種類と探し方【名古屋市の大規模修繕・防水工事は修繕ひらまつ】
名古屋市の融資・利子補給制度とは?

名古屋市では、建物の長寿命化と安全性の向上を目的に「マンション共用部分リフォーム融資分譲マンション修繕工事の融資に対する利子補給事業」を行っています。仮に、通常2.0%の金利で融資を受けた場合に市が0.5%を利子補給すれば、管理組合が負担する金利は1.5%になります。
工事費の負担ではなく利子の一部を負担してくれるのが特徴
特徴は「工事費そのものを補助する制度」でなく「借入金の金利負担を軽くする制度」である点です。1年単位で見ると差は小さいものの、10年スパンで見ると差は大きくなります。
仮に、数千万円規模の融資だと数十万円単位の節約が可能です。「やるべきタイミングで補修する」体制をつくるうえで、効果的な制度だといえます。
対象となる工事の範囲
対象は「共用部分の修繕・改修工事」です。主な事例は次の通りです。
- 外壁・屋上・バルコニー・共用廊下などの防水・外装改修
- 給排水管・受水槽・ポンプユニットなどの設備更新
- LED照明への更新、防犯カメラ・オートロックなどの防犯・省エネ対策
- エレベーター改修、スロープ設置などのバリアフリー工事
- 耐震補強工事、避難経路の改善など安全性向上のための工事
いずれも「建物の機能を維持・向上させること」を目的とした工事が中心です。周期的に実施する外壁塗装やシーリング打ち替えといった大規模修繕、長期修繕計画に沿って複数回にわけて実施する屋上防水や配管更新なども、条件を満たせば対象になります。ただし年度によって、対象の工事が変わる可能性もあるため、申請時に確認しておくことが大切です。
「どの部分が傷んでいるのか」「数年後を見据えた際、どこを優先すべきか」を整理し、制度の対象になる工事とならない工事を切り分けながら、融資計画を組み立てましょう。
名古屋市の融資・利子補給制度のメリット

融資・利子補給制度を使うと、さまざまなメリットがあります。3つにわけて説明します。
①積立金不足を補える
管理組合の方とお話ししていると「積み立てていたのに工事の見積もりを取ると足りない」という声を耳にします。長期修繕計画を立てた当時と比べて物価や工事単価が上がっていたり、想定していなかった下地補修や設備更新が必要になっていたりなど理由はさまざまです。
私は物価が上がっている今こそ、融資を上手に使うことをおすすめしています。融資を活用すれば、必要な修繕費用を一度に確保できるため、住民から費用を徴収できなくても、修繕工事を行うことが可能です。
「お金が足りないから工事をあきらめる」ではなく「融資で建物の劣化を食い止める」といった形で、前向きな決断ができます。
▼資材高騰時代の長期修繕計画の立て直し方はこちら▼
名古屋市の管理組合必見!資材高騰時代に対応する長期修繕計画の立て直し方
②実質金利が低く、長期返済が可能
名古屋市の利子補給制度では、最大1%の金利が名古屋市から補給されます。民間金融機関から通常の条件で借入を行う場合と比べると実質的な金利負担が下がり、毎月の返済額に無理が出にくくなるでしょう。
返済額が減れば、返済期間中であっても「次の大規模修繕に向けた積立」をしやすくなるため、無駄に補修を延ばさなくて済むでしょう。よって「資金不足によって修繕作業が回らなくなった」という状況を避けたい方におすすめです。
なお、適切な返済額を知りたい方は「資金計画のシミュレーション」を行うと良いでしょう。毎月の返済額やトータルの支払額などを把握できるため、無理のない資金繰り計画を立てたい管理組合に向いています。
③修繕計画の透明性が高まる
利子補給制度を利用するには、名古屋市と金融機関の審査を通過する必要があります。審査内容として、次の項目が見られると思った方が良いでしょう。
- 工事の内容や仕様
- 見積金額の妥当性
- 資金使途の明確さ
- 長期修繕計画との整合性
修繕工事計画が大雑把だったり、融資金額を適当に設定したりすると審査に通過しにくくなる恐れがあるため、専門家を交えながら作成することをおすすめします。
制度を活用した修繕の実績が積み重なれば「計画的に修繕と資金管理を行っている」という評価になり、次回以降の融資においてプラスの印象を持ってもらえるかもしれません。さらに、マンションの管理をしっかり行っているという印象を持たれれば、建物全体の資産価値の維持・向上にもつながると考えています。
私は「お金の流れも含めて透明性の高い修繕」を、一つでも多くのマンションで実現していただきたいと考えています。そのためにも、融資・利子補給制度を使いこなすことは大切です。
「お金が足りないから工事をあきらめる」ではなく「融資で建物の劣化を食い止める」といった形で、前向きな決断ができます。あわせて、修繕積立金そのものの水準や設定方法を見直したい場合は、下記のコラムでリスクと対策を整理しています。
▼合わせて読みたい▼
管理組合における修繕積立金不足問題とリスクマネジメントの実務
「マンション共用部分リフォーム融資分譲マンション修繕工事の融資に対する利子補給事業」の申請~利子補給までの流れ

3つのステップにわけて、制度を利用する際の手順を見てみましょう。
①修繕計画と借入方針を決めて、市に「事前相談」する
管理組合として、どの共用部をどのくらいの規模で直すか、長期修繕計画と見積もりを固めます。その後名古屋市に、事前相談・事前協議を申し込みます。
なお、事前協議前には「名古屋市マンション共用部分リフォーム融資利子補給事前協議書」を提出する必要があるため、記入しておきましょう。
②機構の融資を申し込み、市へ「利子補給の資格申請」を出す
住宅金融支援機構の「マンション共用部分リフォーム融資」を管理組合名義で申込みます。申込書の控えなどがそろったら、それを添付して名古屋市に「利子補給の資格申請」を提出し、制度の対象として認めてもらいます。
なお、資格申請時に必要となる主な書類は次の通りです。
- 資格申請書
- 管理規約の写し
- 共用部分リフォーム融資借入申込書の写し(機構の受付日入り)
- 工事見積書の写し
- 長期修繕計画の写し(未整備の場合は後日提出+誓約書)
- 修繕積立金残高が分かる直近の決算書の写し
- 利子補給申請について決議した議案書・議事録の写し
- 建物の登記事項証明書など
提出漏れがあると、利子補給までに時間がかかってしまうため前もって用意しておきましょう。
③工事→機構と正式契約→毎年「利子補給」を申請する
審査が通ったら、施工会社と工事契約を結んで工事を実施します。工事完了後に住宅金融支援機構と金銭消費貸借契約を結び、返済が始まる前に名古屋市へ初年度分の「利子補給交付申請」をすると、利子が補給される流れです。
その後は、毎年度「利子を払う→実績報告と交付申請→名古屋市から利子補給金が振り込まれる」という手順で利子補給されます。なお、最長で10年受けることが可能です。
FAQ|名古屋市のマンション修繕向け融資・利子補給制度についてよくある質問

名古屋市の「マンション共用部分リフォーム融資分譲マンション修繕工事の融資に対する利子補給事業」は、分譲マンションの長期修繕計画と資金計画を両立させるうえで有効な手段の一つです。
一方で、「自主管理の管理組合でも利用できるのか」「どこまでが対象工事に該当するのか」など、制度の具体的な運用面についてご不明点をお持ちの管理組合様・事業者様も少なくありません。以下では、制度活用の検討段階でよくいただくご質問を、実務の流れに沿ってQ&A形式で整理いたしました。
Q.名古屋市の利子補給制度はどのようなマンションが対象になりますか?
原則として、名古屋市内に所在する分譲マンションであり、管理組合名義で共用部分の修繕・改修を実施する案件が対象となります。専有部分のみを対象としたリフォームや、一部区分所有者単独で行う工事は対象外です。
また、住宅金融支援機構の「マンション共用部分リフォーム融資」を利用していること、長期修繕計画と整合性のある修繕内容であることなど、いくつかの要件を満たす必要があります。個別要件や取扱いは年度により変更される場合があるため、申請前に最新の募集要項・ガイドラインを確認することが重要です。
Q.どのような工事が利子補給の対象となりますか?
対象は共用部分に係る修繕・改修工事です。具体的には、外壁・屋上・バルコニー・共用廊下等の防水・外装改修、給排水管・受水槽・ポンプユニット等の設備更新、LED照明や防犯カメラ、オートロックの導入等の省エネ・防犯関連工事、エレベーター改修やスロープ設置等のバリアフリー化工事、耐震補強工事などが挙げられます。
長期修繕計画に基づいて行う大規模修繕や配管更新も、一定の条件を満たすことで対象となるケースが多く見られますが、年度ごとの要件変更もあり得るため、事前相談の段階で対象可否を確認されることを推奨いたします。
Q.管理組合として制度活用を検討する際、最初に着手すべきことは何ですか?
第一に、長期修繕計画と現状の劣化状況を踏まえ、工事範囲・工事規模・実施時期を整理することが重要です。そのうえで、修繕積立金残高と今後のキャッシュフローを確認し、「いくらを融資で賄うのか」「返済期間・返済額の許容範囲はどこまでか」といった借入方針を明確にします。
方針が固まった段階で、名古屋市への事前相談・事前協議を行い、「名古屋市マンション共用部分リフォーム融資利子補給事前協議書」を提出します。これらのプロセスを丁寧に進めることで、その後の資格申請・利子補給申請が円滑になりやすくなります。
Q.申請書類が多く不安です。実務上の注意点はありますか?
資格申請時には、管理規約の写し、共用部分リフォーム融資の借入申込書写し、工事見積書、長期修繕計画、修繕積立金残高の分かる直近期の決算書、総会決議の議案書・議事録、建物の登記事項証明書等、多数の書類を整備する必要があります。実務上のポイントは、「工事内容・工事金額・資金使途・長期修繕計画との関係性」が第三者から見ても明確であることです。
記載内容の不整合や添付漏れがある場合、審査期間の長期化や差し戻しのリスクが高まります。修繕ひらまつでは、チェックリストの作成や書類整理のサポートを行い、管理組合様の事務負担軽減を図ることも可能です。
Q.利子補給は最長10年とのことですが、制度改正があった場合の影響はありますか?
利子補給は原則として最長10年間受けることができ、その間は毎年度「利子支払→実績報告・交付申請→利子補給金の受領」というサイクルで運用されます。制度改正や要件変更が行われる場合もありますが、通常は交付決定を受けた案件については、当該決定時の条件に基づいて利子補給が行われます。
一方で、報告義務を履行していない場合や、資金使途が当初計画から逸脱した場合には、交付対象外となるリスクも想定されます。そのため、制度利用期間中の運用ルールを理事会・管理会社と共有し、継続的に遵守していく体制構築が求められます。
修繕ひらまつへご相談を|名古屋市の制度を活用した無理のない修繕計画を

名古屋市の融資・利子補給制度は、修繕積立金だけでは対応が難しい大規模修繕や設備更新に対し、「必要なタイミングで必要な修繕を確実に実施する」ための有効なファイナンス手段です。一方で、工事内容の精査、長期修繕計画との整合性の確保、理事会・総会での合意形成、さらに名古屋市や住宅金融支援機構への各種申請業務など、管理組合様や管理会社様だけで対応するには負荷の高いプロセスも少なくありません。
修繕ひらまつでは、外壁・防水・設備更新等の技術的検討から、長期修繕計画・資金計画のシミュレーション、事前相談用資料・申請書類の作成支援まで、名古屋市の制度活用を前提とした修繕スキームを一体的にご提案いたします。問い合わせフォームからのお問い合わせはもちろん、メールやお電話でのご相談も承っており、個別の案件についてはショールームでの詳細な打ち合わせも可能です。
「利子補給制度を前提とした資金計画を検討したい」「長期修繕計画の見直しと併せて制度活用を検証したい」といったご要望にも、修繕ひらまつが専門的な立場からサポートいたします。名古屋市での分譲マンション修繕において、財務面と技術面の両側面からリスクを抑えたい管理組合様は、ぜひ一度修繕ひらまつまでご相談ください。
▼合わせてチェック▼
修繕ひらまつ|ショールーム案内